
写真家 HIROKO MATSUBARA

ララガンのデザイナーである高橋れいみさんが絶大な信頼を寄せる写真家・松原博子(以下まっちゃん)は、2021年AWからララガンのルックを撮影している。私とは、家族ぐるみの友人であり、ある時はファッション誌の連載を共に担当し、毎月のように会っていた仕事仲間でもある。人々を魅了する作品をつくるまっちゃんのクリエーションにおける哲学を探るべく話を聞いた。ひさしぶりに会う元アシスタントでPhilosopherの写真撮影を担当しているカメラマンのイムさんも同席しており、気心の知れた者同士が作り出すリラックスした空気が漂っていた。
自分を語ることに対しての独特な距離感を持つ女
子供の頃はいたって普通であり、特に目立った個性があったわけではないというまっちゃんに、写真を撮り始めたきっかけを聞いてみると「とくにないかな。あの頃はみんな撮っていたよね?」という気の抜けるような答えが返ってきた。彼女と同世代である私の記憶では、世にインスタントカメラが出てきた頃であり、ガーリーフォトや女の子写真といった言葉と共に、若い女性の写真家がメディアに多く取り上げられていた。ただし、彼女がどこまであの時代の空気に影響されていたかはわからない。
まっちゃんにインタビューするのは今回で二度目だが、いつも自分を語ることに一定の距離感を持っている印象を受ける。「松原さんは写真で哲学を表現しているから、自分のことを語るのが苦手なのだと思います」という高橋さんの言葉がそのヒントになるかもしれない。「自分のことを語らないながらも、いざ写真を撮ることになれば、期待以上の写真を撮ってくれる安心感がある」と高橋さんは続けた。
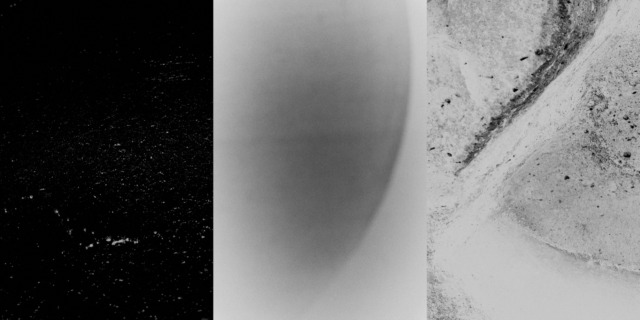
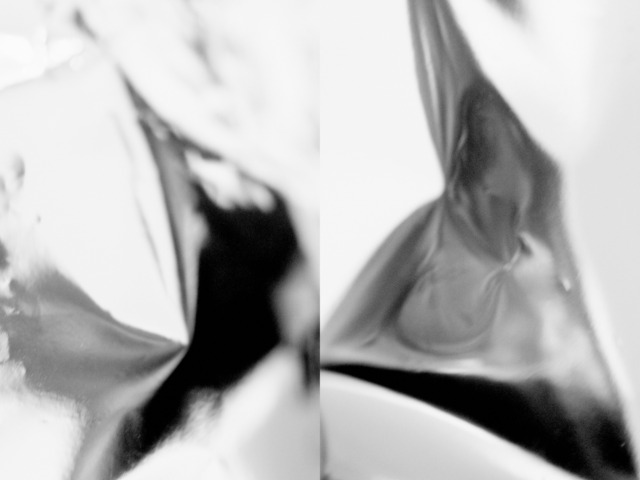
アシスタントだった僕から見た写真家・松原博子
高橋さんと同じように、まっちゃんの才能とその魅力に取り憑かれた者として、二年間アシスタントとして彼女の仕事を見てきたイムさんの言葉を紹介したい。
「松原さんの中には、いろんな点が混在していて、ご本人はあえて言語化しないのですが、彼女の内に存在する宇宙に混在しているものが圧縮され、エネルギーの塊になって外に出てくる。壮大で強いエネルギーを秘めた人」
イムさんは師としての彼女を、母性が強いと感じることも多かったと話す。「単純に母親としての母性ではない、もっと大きな意味の母性。周りの人に陽のエネルギーを自然と分け与えられる人と言いますか、人への愛みたいなもの」
また別の角度から、「松原さんは流動的なイメージがあります」と彼女が周りに放つパワースポット的な気の流れついてもずっと感じていたという。「自然界では、川が流れることによって砂が堆積していき、地盤が固められていくっていう過程があるとして、松原さんの川って、もちろんこだわりとかとても強い方だと思うのですが、全然頑固な人じゃなく、すごくいい流れを持っているから、強さもあるんだなって僕は思います。」「松原さんは何かに縛られることを嫌う。社会に溶け込んだ方が表面的には楽に自由に生きられるのではないかと考える僕に放った「嫌なものは嫌だよね、イムくん」という言葉には、優しさのほかに、社会のルールに迎合しない彼女の内側にある騒ぎや踊り、心臓が動いているようなものを感じます」

私の人生は風雲たけし城!
この言葉は、どうしたら松原博子のような写真家になれるのか?に対する答えだ。「扉を開けたら、そこはダメでも次また挑戦、って言ってどんどん進んできた。考えるより、飛び込んじゃえ!直感で!みたいな」子供の頃にテレビで見ていた視聴者参加型のアトラクションバラエティ番組のことを言っているのだが、行動することで自分の人生を切り開いてきた彼女らしい答えだと思う。
考えるよりも飛び込むことを体現してきた彼女に、仕事を選ぶ基準はあるのだろうか?過去の作品を少なからず見てきた私には、どんな仕事であっても考えなしに扉を開けて飛び込むわけではないと思った。
「仕事を受けるかどうかは、依頼してくれた人が情熱があるかどうかで判断する。高橋さんは、ルック撮影のための衣装を自分で一からデザインしたり、ケータリングのクッキーを自分で理想の型から作っちゃう人なんだよ」高橋さんのクリエーションに対する情熱に共感していることは、照れることなく、まっすぐ語っていたところにもまっちゃんのチャーミングさが滲み出ている。
「あと、モデルは自分で選びたい」「モデルを自分で選べる仕事はうまくいく」まっちゃんにとってモデル選びを全面的に任せてもらえるかどうかは、仕事を受ける時のもうひとつの判断基準になっている。モデル選びは写真の仕上がりに大きな影響が出るほど大事なことである。「コンサバなモデルは好まないということですか?」という高橋さんの質問に「コンサバなモデルは好きだ」と即答している。いわゆるコンサバと表現されがちな、日本のファッション誌ではあまり起用されないタイプのモデルであっても、彼女が良いと思えばうまくいく。新しいものを生み出せる。自らの直感信じ、考えるのをやめて飛び込んでいく。
20代の頃に刺激を受けたもの
「この3つは、私のきっと写真の基本になっているのかもしれない。身体の表し方として」

Erwin Wurm (エルヴィン・ヴルム)の作品集
「人々が彫刻のように感じる Sculptureシリーズが好きです。
One minute sculpture ,Indoor sculptureなど、いろんな場所で、寝たり何かに埋まったり、寝転んだり逆立ちしたり、寄りかかったり。
えー!!!!って驚いたり、クスッと笑わせてくれる。
いつみても飽きない作品。いろんな身体の形。完全じゃないものだから好きなのかもしれません」

Pipilotti Rist (ピピロッティ・リスト)の Ever is over All
「20代の頃ニューヨークで見て、好きになった作品です。
水色のワンピースに赤色の靴で、笑顔で、車の窓ガラスをお花のような植物で割っていくという、ドキドキしちゃうけど、痛快な作品。
警察とも笑顔で挨拶をしながら、窓ガラスを堂々と割って行く姿は、
パワフルだなーってスキップしたくなる。自由って良い」

Pina Bausch(ピナ・バウシュ)のCafe muller
「pinaが踊るのを生で見られた作品です。
動を表しているのではなく。静をダンスで表現していると思いました。
夢遊病のように歩いていく姿は、見つけようにも見つけられない、寂しさや孤独。
身体で言葉を語る。骨や筋肉全てに力を通す。
何を思ったのか、迂闊にも大泣きしてしまいました」
HIROKO MATSUBARA / 松原 博子
フォトグラファー。京都生まれ。
戎 康友氏に師事し、 2009 年に独立。雑誌、広告で活動中。
www.hirokomatsubara.com
Photography_DAEHYUN IM
Interview&Text_TOSHIE KAWAMURA
